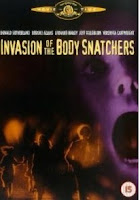書くことについて

The task of an author is, either to teach what is not known, or to recommend known truths by his manner of adorning them; either to let new light in upon the mind, and open new scenes to the prospect, or to vary the dress and situation of common objects, so as to give them fresh grace and more powerful attractions, to spread such flowers over the regions through which the intellect has already made its progress, as may tempt it to return, and take a second view of things hastily passed over, or negligently regarded. と、サミュエル・ジョンソンは言いました。同感ですので、今までのブログポストも、それを旨に書いてきたつもりです。自分で、どこまで目指すとおりに書けているかどうかは、わかりませんが。(上の文は、面倒なので、訳はしません。) サミュエル・ジョンソンはまた、こうも言いました。 No man but a blockhead ever wrote, except for money. 金銭を目的にせずに書くのはバカ者だけ。 ブログをする上で、金銭的に見返りの無いのは覚悟ですが、精神的な見返りも、ほぼ0に近いと感じる昨今、そんな作業にエネルギーを費やすのは、これは、私は、本当にblockheadかもしれない。 少しでも良いものを書こうと、時間とエネルギーをかけるに値する行為か? その時間とエネルギーを他の物に向けたほうが意義が無いか? ただの、骨折り損のくたびれもうけ? 所詮、個人でやっているブログなどに、いいと思うような物を書いたところで、ヒットのみを目的とするようなサイトや個人に、時に、コピーペイストされて、どこかで無記