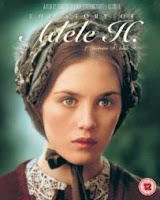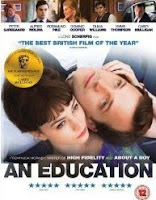美術館内のカメラ使用一考

ロンドンのナショナル・ギャラリー(National Gallery)が館内でのカメラ使用禁止の規制をなくした、というニュースが昨日のロンドン紙イブニング・スタンダードに載っていました。最近は、タブレットやスマホで、絵に関する情報を読んでいるふりをしながら、禁止に関わらず、さりげなく写真を撮っている人も増えている上、監視官が、実際写真を取っているかどうか判定しずらい、それらの人々をすべて、いちいち尋問していられない、という状況が大きな理由のようです。禁止の規制がなくなることにより、絵画の前で セルフィー (自分撮り)をする人の増加を懸念し、実物の絵をじっくり見たいタイプの人々から不満の声が上がっています。そして、そのうちに、ナショナル・ギャラリーは、絵をじっくり見るどころか、名画に背を向けて、それと一緒に自分撮りする、セルフィーのメッカ(selfie central)と化すのでは、との憂いを持つ人もおり。 美術館内のカメラ使用・・・というとすぐ思い起こすのは、 ルーブルのモナリザ ですね、何と言っても。現在のルーブルの方針はわかりませんが、私が行った時は、比較的小さなモナリザの前は押すな押すなの人ごみで、ほとんどの人がカメラをむけていた。つられて、私も、これは、取ったほうがいいか・・・とやはり取ってしまったのだから、「あんな、ミーハーなやつらと、私は違う」なんてえらそうな事はここでは書けない次第。「行った、見た、取った」という証明のためにカメラをむける人がほとんどだったでしょう。たとえ私が取った上の写真のように、ピンボケでも。後で、絵葉書でも買ったほうが、細部まで良く映っていて、鑑賞にはそっちの方がいいにもかかわらず。実際、人ごみの上に、あのカメラずくめでは、じっくり鑑賞しようにも、できない、というのが事実でした。 ルーブルでは、他にも、好きな画家、シャルダンなどの絵の写真も取ったのですが、こちらの絵の前は、人っ子一人おらず、記念の写真を撮った後に、じーっくり、まじまじと眺める事も出来、大満足でありました。人気あるはずのフェルメールの「レースを編む女」の絵の前にも、なぜか、ほとんど人がいなかったのが、いまだに、とても印象に残っているのです。有名な絵・・・を何が有名にするのか、というのは不思議なものです。絵としては、フェルメールやシャルダンの絵の方が、眉...