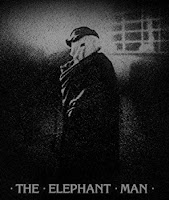ホブスンの婿選び

英語で、「Hobson's Choice」(ホブソンの選択)という言葉があります。どういうことかというと、一見、選択肢があるようでいながら、実はひとつしか選べるものが無く、それを取らないと、何も手に入らない、という状況を表現する時に使われます。 1954年のデイヴィッド・リーン監督のイギリス映画に、その名も「Hobson's Choice」(邦題は、ホブスンの婿選び)というものがあります。(ここで、また、英語のカタカナ表記の問題にいきあたります。私は、個人的には、ホブ ス ンでなく、ホブ ソ ンと書きたいところですが、日本での、この映画の題名は、上記の通り「ホブ ス ンの婿選び」。以下、ホブスン、ホブソンと入り混じれて書いていますが、いずれの場合にせよ、Hobsonの事ですので、悪しからず。) この「Hobson's Choice」という表現の由来は、映画より、もっと古い時代に遡ります。それは、ケンブリッジで厩を経営していたトマス・ホブソン(1544-1631)。馬の数は、40頭はいたというのですが、客には馬を選ばせずに、常に、その客が来た時に、戸口に一番近い馬を貸したという話。というのも、自由に客に選択させてしまうと、常に良い馬が選択されて、その馬のみが、酷使されてしまうため。この事から、選択肢が沢山ありそうでいながら、実はたったひとつしかなく、それを取らなければ、他に何も手に入らない状態の事を、いつのころからか、「ホブソンの選択」と表現するに至ったというのです。という事は、当時、このトマス・ホブソンの商売方法は、語り継がれ、あちこちへ、ひろまっていたのでしょう。トマス・ホブソンなる人物は、特に他に何をしたわけでもなく、有名人物でもないのに、風評というものの力はすごいです。 さて、それでは、私は大変気に入っている映画「ホブスンの婿探し」に話を移します。舞台は19世紀後半の、イングランド北部、ランカシャー州の町サルフォード。産業革命で、織物業などが栄えた町で、映画内、古びた商店がならぶ、石畳の、町の目抜き通りの風景には古き良きイングランド的、レトロ感漂うものの、町の郊外の背景には、工場の煙突などが伺えます。 ざっとしたあらすじは、 チャールズ・ロートン演じる、呑み助のホブソン氏は、町の目抜き通りで靴屋を経営。もっとも、...