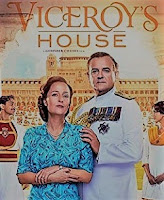映画「女王陛下のお気に入り」とアン女王

スチュアート朝最後の君主、アン女王の治世を舞台とする映画、「女王陛下のお気に入り」(The Favourite)を見に行きました。宮廷に仕える二人の女性、セーラ・チャーチル(Sarah Churchill)とアビゲイル・ヒル(Abigail Hill)が、アン女王の寵愛、ひいてはそれに伴う政治力をめぐって、女の戦いを繰り広げるコメディーで、国の方針が、この3人の女性の関係によって、影響を受ける様子を追っています。 3人の女性たち、アン女王は普通のおばさん風女優オリヴィア・コールマン、セーラ・チャーチルは、ちょっとした男装もいかしていたレイチェル・ワイズ、そしてアビゲイル・ヒルは、大きな目玉のエマ・ストーンが演じています。オリヴィア・コールマンという人は、ノーフォーク州の ノリッチ 出身なのですが、ノリッチで有名な、辛子の製造業社コールマンズ(Coleman's)と関係があるのかと思ったら、関係はないようです。同じ土地で、同じ名前が多いという事は時々ありますしね。 一応、歴史ドラマ風ではありますが、史実とは違う事を取り入れたり、さらには憶測に基づいて書かれており、歴史もの映画の全てに言えることかもしれませんが、半分は作りものと思って見ていた方が無難です。ただ、チューダー朝のエリザベス1世やヘンリー8世がらみの映画やテレビドラマは星の数ほどあるので、アン女王が主人公というのは画期的です。 ***** 時代背景をなんとなく知っておくために、アン女王と、映画の元となっている、彼女の時代の史実を、簡単に、下にまとめておきます。 アン女王は、姉のメアリーと義理の兄ウィリアム3世亡き後、1702年に女王となり、君臨する事12年間。1707年には、合同法(Act of Union)により、スコットランドがイングランドに統合され、グレート・ブリテン王国となるため、彼女は、グレート・ブリテンの初めての君主ということにもなります。いわゆる ユニオンジャック が国旗として使用されるようになるのも、この時から。 夫君は、デンマーク出身のカンバーランド公ジョージ。ウィリアム3世などからは、「箸にも棒にも掛からぬ男」の様に見下されていたようですが、政略結婚にもかかわらず、夫婦仲は良好であったようです。17回(一説では18回)の妊娠を繰り返しながら、流産、死産が...