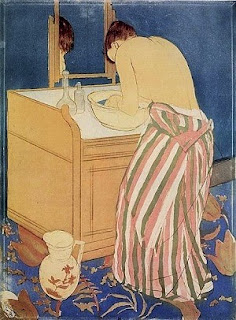自転車泥棒

ここしばらく、ヨーロッパ映画を見ていないな、とふと思い、見たのが、これ、1948年公開、ヴィットリオ・デ・シーカの「自転車泥棒」。現代の若い人たちも、まだこういう映画を見ているのかは、知りませんが、未だに、傑作映画の呼び声高い、戦後間もないローマを舞台にした、切ない話です。このくらいの時代の映画は、イギリス映画もそうですが、まだ戦争の傷跡残る都会の風景が印象的。 あらすじは、いたって簡単。職を探す人々の波が職安にたむろしている場面から始まります。ここで、ついに、待ち望んだ仕事を得たアントニオ。ただし、移動しながら、街中にポスターを張る仕事であるため、自転車を持っていることが条件。そこで、妻は、ベッドに敷いてあったシーツなどを引っぺがし、それを質に入れて、その分で、以前、質に入れてあった自転車を取り戻す。シーツは無くなったけど、妻と小さな息子ブルーノも大喜び。翌朝は、張り切って仕事に出たはいいが、仕事半ばで、壁に立てかけてあった自転車が盗まれてしまう。映画の残り部分は、この自転車を見つけ出すため、アントニオとブルーノが、あちこちを奔走することになります。そして、最後に、絶望したアントニオが、自分自身、自転車を盗もうとしてしまう。 自転車が盗まれた直後、アントニオは、警察に届け出るのですが、記録を取った後は、見つかったらまた届けろ、と言うだけで、何をしてくれる様子もない。「探してくれないのか」の問いには、たくさんある自転車から、お前のを探せるわけがない、自分のなんだから、どんなのかは自分で知ってるだろう、もう、リポートすんだから、帰れ、のようなことを言われる。こんなやり取り、笑いながら見てました、今でも、基本的に同じだから。 財布やら貴重品をイギリスやらヨーロッパで盗まれても、警察に届けるだけ時間の無駄。今年の夏、お隣さんはオックスフォードまで車で出かけ、どこかの公共の駐車場に止めた際、彼のホンダ車の下から、三元触媒コンバーターがもぎとられ、盗まれてしまったという事件に会っています。なんでも、日本車のコンバーターは性能が良く、被害にあいやすいとか。こんなのも、埒もあかないと、警察に届けたりしなかったようです。警察も資金不足、人手不足の昨今ですから。数年前に、空き巣に入られた友人は、おじいさんの第一次世界大戦のメダルを盗まれたそうで、これはさすがに警察に届け出。...