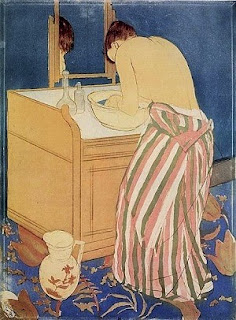かき氷の旗に誘われて

暑い日は、引き寄せられる、かき氷の旗 昨日は、イギリス南部もついに30度に突入し、ヒースロー空港では、今年最高の34度を記録。慣れていないと、30度でも、暑い・・・のです。もっとも、熱波も一日で終わり、本日は、おとなしく、25度くらいにとどまってくれるようですが。 日本に 前回帰国 したのは去年の6月だったな、結構暑かったな、とその時取った写真に、久しぶりに目を通し、ふと気になったのが、上の写真。アスファルトも熱する街中を歩き回っている時、かき氷の旗に、涼しさを感じて、写したのだと思います。(ちなみに、旗は裏側から取っていますので、氷の字はひっくり返っています。)これを、しげしげ眺めていているうち、デザインの中に、波のしぶきのようにして、千鳥が組み込まれているのに、今更気が付きました。氷という字は赤で、涼やかさを連想させる色ではないのですが、遠くからも良く見える。涼感は、旗の下の、 北斎の波 のような、青いうねる海のデザインをもってして、かもし出しています。考えてみるに、こういう、全国つづうら浦、定番のデザインで、ぱっと見て「お、あの店でxxを売っている。それ行け!」と、わかるようなもの、イギリスでは考え付きません。遠くからでも、それとわかる、このかき氷の旗は、かなりのすぐれものです。こういうのを見ると、日本は、デザインや図形で、簡潔に、言いたいことを伝達をする術が、優れた国なのだと思います。今では、すっかり英語にもなっている、「絵文字」なんてのも、発祥が日本というのは、こうした文化が背景にあるからですね、きっと。 この写真をきっかけに、かき氷、ひいては、氷というものの歴史をちらっと調べて見ました。 かき氷の事を、一番最初に書きしたためてある文献は、清少納言の「枕草紙」であると言います。冷蔵庫などが無い時代は、真夏の都市で、氷を入手する事、しかも、それをかき氷にして食べる、などというのは、富裕階級、貴族階級のみができた事。雪国では、冬季に、凍った池や湖などから氷を切り出し、氷室に貯蔵することなどが可能であったものの、それを、溶かさないように移動するのは、大変です。よって、雪国から遠く離れた都会に住む一般庶民には、かき氷は、長い間、ほとんど縁のない食べ物であったわけです。 時代すすんで、江戸時代の鎖国が終わると、はるばるボストンから、天然氷のボ