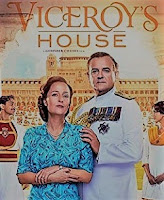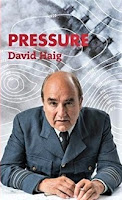霧の中の動物たち~その辺旅行のすすめ

日本の幼馴染から、メールで、イギリスの冬は青空が見えるのか、と聞かれました。なんでも、友達が南ドイツの山岳部を旅行して、青い空を背景に3000メートル級のオーストリアの山並みが見え、とてもきれいだったと聞かされ、そういう所に行ってみたいと思ったのだそうです。イギリスには、3000メートル級の山並みもなければ、冬季の青空も稀。まだ、東京あたりの方が、青空が見える回数は多いはずです。 今年の元日に、家の近くの田舎の散歩に出た時の様子を ブログ記事 にしました。丁度一年ほど経った本日も、灰色の空の下、しかも昼にもなろうというのに、霧の立ち込めた田舎道に散歩に出ました。じとっとしめって、雲が垂れこめた、毎度おなじみ、典型的イギリスの冬の日。比較的暖かかったですが。 歩き始めて、まず、お目にかかったのは、2頭の牛。つぶらな瞳のまつげは白でした。 こちら、威風堂々、横向きポーズ。 木製のゲートを超えて、次に現れたのは、馬たち。普通の馬一頭と、かわいいポニーが2頭。皆、冬用ジャケットを着用。 馬は、必ずと言っていいほど、近づいてくるので、柵から、かなり離れたフィールドの端にいたのに、瞬く間にそばにやって来て、私のすぐそばで、草をバリバリ食べ始めました。 最後に遭遇したのは羊たち。羊は、私が歩いているのに気づくと、起き上がって、こっちを見たりするのですが、馬と違い、臆病なのか、寄っては来ない。でも、ずーっと、視線を感じます。遠巻きに、見えなくなるまで、こちらの様子をうかがっていました。 散歩の後は、近くの町のティールームで、ランチ。これで、結構、幸せな一日。 私も、海外旅行は時々、行きたくなりますが、空港の混雑ぶり、ホテルにチェックインするまでの行程、また、慣れない枕で寝ることなどを考えると、段々、億劫になって来て、若い時ほど、「さー、色々海外行ってみないと!」という強い気持ちは薄れて来た、というのはあります。日本で生まれながら、海外に住んでいるわけですが、人生の半分以上生活している場所は、もう海外とは、呼べないですしね。 以前、 スノーマン 作家のレイモンド・ブリッグズが、「混み混み空港が嫌だから、海外旅行なんてほとんど行かない」というような事をインタヴューで言っていたのを思い出して、「わかる。」という気持ちも強くなって